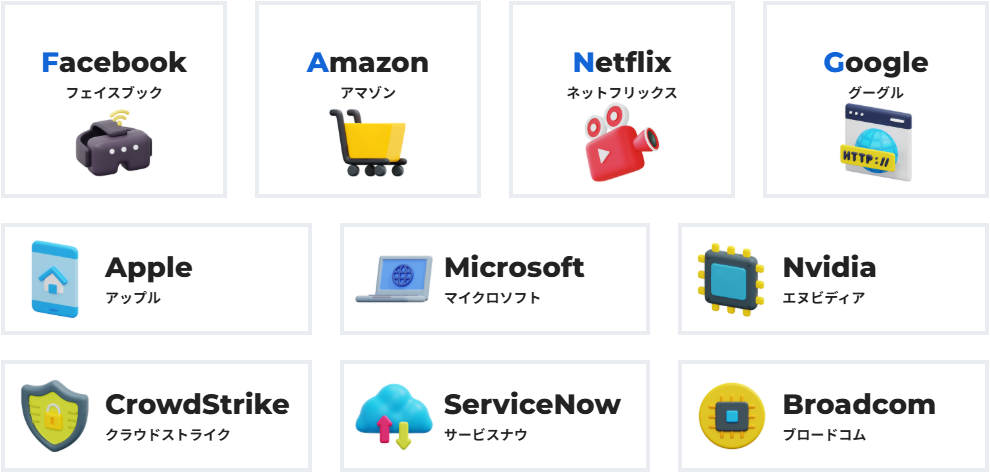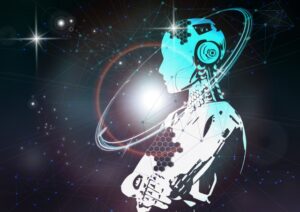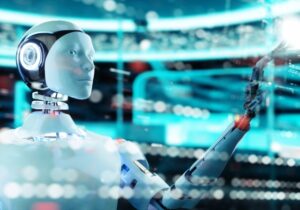「FANG+」と「S&P500」のどっちが長期的な資産形成に向いているのかを知りたい人は多いのではないでしょうか。
このページでは、米国株投資に興味がある初心者から中級者の方を対象に、FANG+インデックスとS&P500インデックスの違い・特徴・リターン・リスク・コストなどを徹底比較していきます。
FANG+とS&P500のどちらに投資すべきか迷っている方や、新NISAでの活用を検討している方にも役立つ情報をまとめています。
最新の運用実績・評判・今後の見通しなど、最適な資産形成法を見つけるための判断材料を紹介するので参考にしてください。
証券会社の口座開設をする際はポイントサイト経由がお得です。
▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼
▼ハピタスの証券広告特集▼
FANG+とS&P500の違いとは?長期資産形成の観点から注目される理由

「FANG+」と「S&P500」はどちらも米国株を代表するインデックスですが、その構成やリスク・リターンの特性は大きく異なります。
FANG+は主に米国の巨大テック企業10社に集中投資するインデックスで、近年の急成長が注目されています。
S&P500は米国を代表する500社に分散投資するインデックスで、安定性と長期的な成長が魅力です。
 ざくざく
ざくざく
投資家が資産形成を目指す際、どちらを選ぶべきかはリスク許容度や投資目的によって異なります。
比較ポイント:FANG+インデックスとS&P500の基本構成
FANG+インデックスは、Facebook(現Meta)・Apple・Amazon・Netflix・Google(現Alphabet)など、米国を代表するテクノロジー企業10社で構成されています。
S&P500は米国の大型株500社を時価総額加重で組み入れており、テクノロジーだけでなく金融・ヘルスケア・消費財など幅広い業種をカバーしています。
この構成の違いがリターン・リスク・値動きの特徴に大きく影響しています。
| インデックス名 | 構成銘柄数 | 主な業種 | 分散性 |
|---|---|---|---|
| FANG+ | 10 | テクノロジー中心 | 低い |
| S&P500 | 500 | 多業種 | 高い |
米国株投資家に人気のFANG+とS&P500の特徴
FANG+は、近年の米国株ブームを牽引してきたビッグテック企業に集中投資できる点が大きな魅力です。
短期間で大きなリターンを狙いたい投資家や、テクノロジー分野の成長性に期待する方に人気があります。
S&P500は、長期的な安定成長と分散効果が魅力で、老後資産形成やつみたてNISAなどの長期投資に適しています。
- FANG+は短期的な成長性・高リターンが魅力
- S&P500は分散性・安定性・長期リターンが強み
- 投資目的やリスク許容度で選択が分かれる
どちらも米国経済の成長を享受できる点は共通していますが、リスクとリターンのバランスが異なるため、投資スタイルに合わせて選ぶことが重要です。
FANG+とS&P500どちらがおすすめしないケース・NISA対応状況
FANG+は、値動きが大きく短期的な下落リスクも高いため、リスク許容度が低い方や分散投資を重視する方にはおすすめできません。
S&P500は、安定性が高いものの爆発的なリターンを狙いたい方には物足りない場合もあります。
- FANG+は短期的な値動きに耐えられない人には不向き
- S&P500は超高成長を狙う人には物足りない
- どちらも新NISA対応ファンドあり
どちらも新NISAに対応しているファンドがあるため長期積立にも活用可能です。
出典:金融庁
自分の投資目的やリスク許容度に合わせて選択しましょう。
FANG+インデックスの概要と魅力
FANG+インデックスは、米国の代表的なテクノロジー企業10社に均等投資するユニークなインデックスです。
FANG+の魅力は、世界をリードする企業の成長をダイレクトに享受できる点と、少数精鋭の集中投資による高いリターンです。



一方で、値動きが大きくリスクも高いため投資判断には注意が必要です。
ifreeNEXT FANG+インデックスなどの投資信託を通じて、手軽に投資できる点も人気の理由です。
ファングプラス(FANG+)の対象銘柄と構成比率を解説
FANG+インデックスは、米国のテクノロジー分野を代表する10社で構成されています。
2025年8月時点では、Meta(旧Facebook)・Amazon・Apple・Netflix・Google(Alphabet)・Microsoft・NVIDIA・CrowdStrike・ServisNow・Broadcomが含まれます。
出典:大和アセットマネジメント
各銘柄の比率は均等(各10%程度)でリバランスされるため、特定の企業に偏りすぎるリスクを抑えています。
FANG+インデックス入れ替えルールは年2回(3月・9月)で、基準を満たさなくなった銘柄は除外されて新たな有力テック企業が組み入れられる仕組みです。
各銘柄の構成比率は均等(各10%)で、特定の企業に偏りすぎない設計となっています。
この均等配分によりどの企業の成長もリターンに大きく反映されるのが特徴ですが、いずれもハイテク・IT関連企業であるため業種分散は限定的です。
ifreeNEXT FANG+インデックスの特徴と運用実績
ifreeNEXT FANG+インデックスは、日本国内でFANG+インデックスに連動する代表的な投資信託です。
このファンドは、FANG+指数の値動きに連動する運用を目指し少額からでも投資できる点が魅力です。
過去の運用実績を見ると、2020年以降のテック株ブームで大きなリターンを記録しています。
- FANG+指数に連動する日本の代表的ファンド
- 少額から積立投資が可能
- リターンは高いが値動きも大きい
ただし、2022年の米国金利上昇局面では一時的に大きく下落するなど値動きの大きさも特徴です。
信託報酬はやや高めですが成長性を重視する投資家に人気があります。
FANG+のリターン推移・成長性・注目ポイント
FANG+インデックスは、過去10年間で約20倍に成長したという圧倒的なリターン実績があります。
これはS&P500やNASDAQ100を大きく上回る成績です。
2020年以降のAIブームで構成銘柄の株価が急騰し、短期間で大きな資産増加を実現した投資家も多いです。
一方で2022年のような調整局面では大きく下落するリスクもあり、ボラティリティの高さが特徴です。
| 期間 | FANG+リターン | S&P500リターン |
|---|---|---|
| 過去10年 | 約20倍 | 約5倍 |
| 2020年~2025年 | 大幅上昇 | 堅調上昇 |
FANG+はやめとけ?リスク・注意点・よくある評判
FANG+は高いリターンが期待できる一方でリスクも大きいという声が多いです。
構成銘柄がテクノロジー分野に集中しているため、業界全体の逆風や規制強化、金利上昇局面では大きく下落することがあります。
また、信託報酬がS&P500系ファンドより高めで、長期保有時のコスト負担も無視できません。
- 値動きが大きく短期的な下落リスクも高い
- 分散性が低く特定業種の影響を受けやすい
- 信託報酬がやや高め
短期的な値動きに耐えられない方や分散投資を重視する方には向かないという評判もあります。
リスク許容度や投資目的を明確にして選ぶことが大切です。
S&P500インデックスの基礎知識
S&P500インデックスは、米国を代表する大型株500社で構成される世界的に有名な株価指数です。
長期的な安定成長と分散効果が魅力で、老後資産形成のために新NISAなどの長期投資に最適とされています。



多くの投資信託やETFがS&P500に連動しており、低コストで手軽に分散投資が可能です。
S&P500の銘柄構成・業種比率と米国市場での役割
S&P500は、米国の代表的な大型株500社で構成されており、時価総額加重平均で組み入れられています。
テクノロジー・金融・ヘルスケア・消費財・エネルギーなど多様な業種がバランスよく含まれているため、米国経済全体の動向を反映する指標として世界中の投資家に利用されています。
特にテクノロジーセクターの比率が高まっているものの、他業種も含まれることで分散効果が高く、長期的な資産形成に適しています。
| 業種 | 比率(目安) |
|---|---|
| テクノロジー | 約28% |
| ヘルスケア | 約14% |
| 金融 | 約12% |
| 消費財 | 約11% |
| その他 | 約35% |
※2025年8月時点
S&P500インデックスファンド・ETFの選び方と特徴
S&P500に連動するインデックスファンドやETFは、運用コストの低さと分散効果の高さが魅力です。
代表的なETFには「VOO」「IVV」「SPY」などがあり、いずれも信託報酬が非常に低く長期投資に適しています。
投資信託では「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」や「SBI・V・S&P500」などが人気です。
- 信託報酬の低さを重視
- 純資産残高や流動性を確認
- 新NISA対応か確認
S&P500のインデックスファンドやETF選ぶ際は、信託報酬・純資産残高・運用実績新NISA対応状況などを比較しましょう。
S&P500投資信託の評判・信託報酬・コスト比較
S&P500連動型の投資信託は、低コストで長期運用に適していると高い評価を受けています。
特に「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」は信託報酬が0.0814%(税込)と業界最安水準で、コストパフォーマンスが抜群です。
他にも「SBI・V・S&P500」や「楽天・全米株式インデックス・ファンド」なども人気があります。
コストの違いは長期運用で大きな差となるため、信託報酬や実質コストをしっかり比較しましょう。
| ファンド名 | 信託報酬(年率) |
|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0814% |
| SBI・V・S&P500 | 0.0938% |
| 楽天・全米株式インデックス | 0.132% |
※2025年8月時点
S&P500運用実績と長期リターンの推移
S&P500は、過去数十年にわたり年率平均7~10%程度のリターンを記録してきました。
リーマンショックやコロナショックなどの暴落局面もありましたが、長期的には右肩上がりの成長を続けています。
- 年率平均7~10%のリターン
- 過去10年で約5倍に成長
- 暴落時も長期で回復傾向
過去10年では約5倍に成長しており、安定した資産形成を目指す投資家にとって非常に魅力的なインデックスです。
分散効果と米国経済の成長力が長期リターンの安定性を支えています。
FANG+とS&P500を徹底比較!資産形成に有利なのはどっち?
FANG+とS&P500は、リターン・リスク・コスト・分散性など多くの面で違いがあります。
短期的な成長性を重視するなら「FANG+が有利」で、長期的な安定成長を重視するなら「S&P500が有利」と言えるかもしれません。



ここからは、それぞれのリターン・コスト・リスクなどの観点から両者を徹底比較します。
自分の投資目的やリスク許容度に合わせて最適なインデックスを選びましょう。
リターン・成長率・時価総額のシミュレーションとチャート比較
FANG+とS&P500のリターン・成長率・時価総額を比較すると、FANG+は短期間で爆発的な成長を遂げてきた一方、S&P500は安定した右肩上がりの成長が特徴です。
過去10年のシミュレーションでは、FANG+は約20倍・S&P500は約5倍に成長しています。
しかしながら、FANG+は値動きが大きく下落時のダメージも大きい点に注意が必要です。
時価総額ではS&P500が圧倒的ですが、FANG+構成銘柄の時価総額も世界トップクラスです。
チャートで比較するとFANG+のボラティリティの高さが際立ちます。
| インデックス | 過去10年リターン | 時価総額(目安) |
|---|---|---|
| FANG+ | 約20倍 | 約10兆ドル(構成銘柄合計) |
| S&P500 | 約5倍 | 約40兆ドル |
※2025年8月時点
信託報酬・費用・負担で比べる!投信・ETFのコスト差
投資信託やETFのコストは長期運用で大きな差となります。
FANG+連動型ファンドは信託報酬が0.77%前後とやや高めですが、S&P500連動型ファンドは0.1%未満のものも多いです。
ETFの場合でもS&P500連動型の「VOO」や「IVV」は超低コストで人気があります。


コスト重視の長期投資ならS&P500が優位ですが、FANG+は高リターンを狙えるためコスト負担も許容できるかがポイントです。
| ファンド名 | 信託報酬(年率) |
|---|---|
| ifreeNEXT FANG+ | 0.77% |
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0814% |
| VOO(ETF) | 0.0938% |
※2025年8月時点
リスク・値動き・ボラティリティの違いを徹底分析
FANG+は構成銘柄がテクノロジー分野に集中しているため、業界全体の逆風・規制強化・金利上昇局面では大きく下落するリスクがあります。
ボラティリティ(値動きの大きさ)はS&P500よりも高く、短期的な資産変動が大きいのが特徴です。
S&P500は分散効果が高く暴落時の下落幅もFANG+より小さい傾向があります。
リスクを抑えたい場合はS&P500を選び、リターン重視ならFANG+が選択肢となります。
| インデックス | ボラティリティ | 主なリスク要因 |
|---|---|---|
| FANG+ | 高い | テック業界の逆風・規制 |
| S&P500 | 中程度 | 米国経済全体の景気変動 |
※2025年8月時点
投資目的に合わせた選び方と運用アイデア
FANG+とS&P500は、それぞれ異なる投資目的やリスク許容度に応じて使い分けることが重要です。
長期積立や老後資産形成にはS&P500が向いており、短期的な成長やテクノロジー分野への集中投資にはFANG+が向いています。



自分のライフプランや資産運用の目標に合わせて最適なインデックスを選びましょう。
長期積立での活用例と資産推移シミュレーション
長期積立投資ではS&P500が安定したリターンと分散効果で高い人気を誇ります。
たとえば、毎月3万円を20年間積み立てた場合、S&P500の年率7%リターンなら約1,500万円に到達するシミュレーションも可能です。
- S&P500は長期積立・つみたてNISAの王道
- FANG+は高リターン狙いの積立に適するがリスクも大きい
- 両者の組み合わせでバランス運用も可能
FANG+は年率リターンが高い年も多く、同じ条件で積み立てた場合は資産が2,000万円を超えるケースもありますが、値動きが大きいため元本割れリスクも高まります。
長期積立ではリスク分散を意識してFANG+とS&P500を組み合わせるのも有効です。
ファンドの選定ポイント(ランキング・残高・パフォーマンスで比較)
ファンド選びでは、信託報酬の低さ・純資産残高の多さ・過去のパフォーマンスが重要な比較ポイントです。
ランキング上位のS&P500連動型ファンドは「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」や「SBI・V・S&P500」などで、いずれも低コスト・高流動性が魅力です。


FANG+連動型では「ifreeNEXT FANG+インデックス」が代表的ですが、信託報酬・純資産残高・運用実績を必ず確認しましょう。
各ファンドの運用方針やNISA対応状況もチェックポイントです。
| ファンド名 | 信託報酬 | 純資産残高 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 0.0814% | 7兆円超 |
| ifreeNEXT FANG+インデックス | 0.77% | 7000億円超 |
※2025年8月時点
FANG+・S&P500以外のテック・米国株インデックスと併用戦略
FANG+やS&P500以外にも、NASDAQ100やS&P500トップ10インデックスなど米国株の成長企業に特化したインデックスがあります。
これらを組み合わせることで、テクノロジー分野の成長を取り込みつつ分散効果を高めることが可能です。
- NASDAQ100はテック中心の分散型インデックス
- S&P500トップ10は超大型株に集中投資
- コア・サテライト戦略でリスク分散と成長性を両立
たとえば、S&P500をコアに据えてFANG+やNASDAQ100をサテライトとして少額組み入れる戦略は、リスクとリターンのバランスを取りやすくなります。
自分の投資スタイルや目標に合わせて複数のインデックスを活用しましょう。
よくあるQ&A・最新ニュースと今後の見通し
ここからは、FANG+やS&P500に関するよくある疑問や、2024年以降の最新動向と今後の見通しについて解説します。
投資信託やETFの構成銘柄変更・純資産推移・米国市場のトレンドなど、投資判断に役立つ最新情報もまとめました。



今後の資産形成戦略を考える上で最新ニュースやQ&Aを参考にしましょう。
ifreeNEXT FANG+インデックス 2024年以降の展望と最新情報
ifreeNEXT FANG+インデックスは、2025年以降もAI・クラウド・EV・半導体などの成長分野を牽引する企業群への投資が期待されています。
特にNVIDIAやMetaなどはAIブームの恩恵を受けており、今後も高い成長が見込まれます。
- AI・クラウド・EV分野の成長がカギ
- 規制や金利動向に注意
- 構成銘柄の入れ替えも定期的に発生
米国の金利動向・規制強化・地政学リスクなどが短期的な値動きに影響を与える可能性もあります。
最新の運用報告や構成銘柄の入れ替え情報を定期的にチェックしてリスク管理を徹底しましょう。
S&P500の直近動向・トレンドと資産形成への影響
S&P500は2023年から2025年にかけて、米国経済の回復やテクノロジー株の好調を背景に堅調な推移を見せています。
インフレや金利上昇の影響を受けつつも、結果的には分散効果により大きな下落は限定的でした。
- 米国経済の成長がS&P500の安定性を支える
- インフレ・金利動向に注目
- 分散効果で大きな下落リスクを抑制
今後も米国経済の成長が続く限りS&P500は長期的な資産形成の中心的存在となるでしょう。
しかしながら、景気後退や地政学リスクには注意が必要です。
人気投資信託・ETFの売買・純資産推移・構成銘柄の変更点
FANG+やS&P500連動型の投資信託・ETFは純資産残高が年々増加しており、個人投資家からの人気が高まっています。
特にeMAXIS Slim米国株式(S&P500)やifreeNEXT FANG+インデックスは、積立投資や新NISA口座での利用が拡大中です。
構成銘柄の入れ替えや比率変更も定期的に行われており、最新の運用報告を確認することが大切です。
売買動向や純資産の推移はファンドの信頼性や流動性の目安にもなります。
| ファンド名 | 純資産残高 | 構成銘柄の変更頻度 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 7兆円超 | 最大年4回 |
| ifreeNEXT FANG+インデックス | 7000億円 | 最大年4回 |
※2025年8月時点
【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ
ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。
ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。
電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。
ハピタスに登録する手順は以下の通りです。
- ハピタス登録の紹介リンクを押す
- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ
- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力
- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力
- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力
- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要
- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要
- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要
- 登録完了
まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。
▼ハピタス登録はこちらからがお得▼
 ざくざく
ざくざく
移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。
QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。
▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼


ハピタスに登録するメリット
ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイントが貯まりやすい
- 1ポイント1円で分かりやすい
- ポイント保証制度が充実している
- ポイント交換手数料が無料
- サイトが見やすく使いやすい
ハピタスの最大のメリットは、日常生活のさまざまな行動を通じてポイントを獲得できることです。
たとえば、普段利用しているショッピングサイトで買い物をするだけでポイントが貯まり、新たにサービスを始める際にもハピタス経由で登録すればポイントが獲得できます。
ハピタスを通じて効率的にポイントを獲得し、それを現金やギフト券などに交換して生活をより豊かにしていきましょう。
ハピタスに登録するデメリット
ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイント反映が遅い
- 会員ランクの昇格・維持が面倒
- コツコツ系コンテンツが少ない
- アプリ版ハピタスが使いにくい
- サイトページの読み込みが遅い
私自身がハピタスを実際に使ってみたデメリットなので、人によっては感じ方が違うと思います。
ハピタスは非常に便利なポイントサイトですが、全てのポイントサイトサービスと同様にいくつかのデメリットも存在します。
これからハピタスを始めてみようと思っている人は、メリットだけではなくデメリットも把握しておきましょう。
ハピタスの利用は計画的に行い、自分のライフスタイルに合った方法でポイントを獲得することをおすすめします。
ハピタスでポイントを貯める方法
ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。
それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。
毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。
- ネットショッピング広告を利用する
- 無料体験系サービス広告を利用する
- リサイクル系広告を利用する
- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する
- 外食モニターコンテンツを利用する
- 友達紹介コンテンツを利用する
ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。
FANG+とS&P500の徹底比較まとめ
- 安定重視ならS&P500
- 成長重視・リスク許容ならFANG+
- 両者の組み合わせでバランス運用も有効
FANG+とS&P500は、それぞれ異なる魅力とリスクを持つインデックスです。
安定した長期資産形成を目指すなら「S&P500」が適しており、テクノロジー分野への集中投資を狙うなら「FANG+」が適しています。



両者を組み合わせてバランスを取る戦略もおすすめですが、自身のリスク許容度・投資目的・運用期間に応じて最適な選択をしましょう。
最新の運用実績や市場動向を定期的にチェックし、柔軟に資産配分を見直すことが成功のカギとなります。
▼ハピタス登録はこちらからがお得▼
▼ハピタスの証券広告特集▼