老後資金を準備するための制度として注目を集める「iDeCo(個人型確定拠出年金)」は、公務員の方にとって 賢く資産を築くための強力な選択肢として急速に普及しています。
2017年1月から公務員も加入可能となり、2024末時点で公務員の加入者数は増加傾向にあります。
かつて公務員は高額な退職金や共済年金の手厚い給付により、老後は経済的に安定と広く信じられていました。
しかしながら、2015年の年金制度改正で共済年金が厚生年金に統合され、職域加算が廃止されたことで年金受給額が実質的に減少し退職金も年々減額されています。
医療費や介護費の上昇が老後の生活コストを押し上げ、自分で老後資金を準備することの重要性を強く認識させています。
このページでは、投資に不慣れな方でも理解できるようにiDeCoの仕組みやメリット・デメリットを解説するので参考にしてみてください。
 ざくざく
ざくざく
▼ハピタスの証券広告特集▼
▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼
公務員はiDeCoに加入すべき? メリットと理由を解説

公務員の方にとってiDeCoは老後資金を効率的に準備するための最適なツールです。
かつて公務員は高額な退職金や職域加算と呼ばれる共済年金の上乗せ給付により、老後の資金に困ることはほぼないとされていました。
しかしながら、2015年の年金制度改正で共済年金が厚生年金に統合され、職域加算が廃止されたことで年金受給額が約1割減少しました。
| 項目 | 内容 |
| iDeCoとは | 掛け金を運用して老後資金を準備する制度 |
| 公務員におすすめの理由 | 年金制度の変更等により老後資金の準備が必要 |
| 利用者数の推移 | 年々増加傾向 |
公務員であっても年金や退職金だけに頼って老後を安心して過ごすのは難しくなっています。
iDeCoは、税制優遇の充実・自動積立の手軽さ・柔軟な運用オプションにより、公務員の皆様が無理なく老後資金を準備できる制度です。
投資未経験の方でも金融機関のサポートやオンライン手続きの簡便さにより、手間をかけずに資産形成を始められる点が大きな魅力です。
iDeCoとは? 公務員が知っておくべき基本
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛け金を拠出し投資信託や定期預金などの金融商品を通じて運用することで老後資金を準備する制度です。
iDeCoの最大の特徴は、税制優遇・掛け金の全額所得控除・運用益の非課税・受け取り時の控除と運用の柔軟性にあります。
- 自分で掛け金を決め運用して老後資金を準備
- 利用状況が年々増加
- 手軽な設計と金融機関のサポートで簡単に始められる
掛け金は毎月自動引き落としで拠出され、自分のリスク許容度や運用目標に応じて低リスクの定期預金から高成長の投資信託まで選べます。
2024年12月から掛け金上限が月12000円から20000円に引き上げられ、より多くの資金を積み立てられるようになり節税効果も拡大しています。
なぜ公務員にiDeCoが必要? 老後資金の現状
かつては高額な退職金と共済年金に含まれる職域加算という上乗せ給付により、老後の経済的な不安はほぼないとされていました。
しかしながら、2015年の年金制度改正で共済年金が厚生年金に統合され、職域加算が廃止されたことで年金受給額が約1割減少しています。
老後2000万円問題がメディアで大きく取り上げられ、公的年金だけでは老後の生活費が不足する可能性が広く認識されるようになりました。
- 職域加算廃止で年金額が約1割減少
- 直近5年で約40万円減 10年前比で数百万円の差
- 老後2000万円問題や生活コスト上昇で自己準備が必要
厚生労働省のデータによると、65歳以上の高齢者世帯の平均生活費は月約25万円で、公的年金だけでは不足する場合が多いようです。
iDeCoはこうした課題に対応し、将来の経済的な不安を軽減するための有効な手段として注目されています。
iDeCoが公務員におすすめの理由
iDeCoは公務員が老後資金を賢く準備するための最適な制度です。
掛け金が全額所得控除の対象で所得税や住民税の負担が軽減され、たとえば年収600万円の公務員が月12000円拠出すると年間約28800円の節税が可能です。
通常の投資では課税される約20.315%の税金が免除され、長期運用で資産が大きく成長します。
- 掛け金全額控除、運用益非課税、受け取り時も控除
- 自動引き落としで手間なく資産形成
- 年金や退職金の不足を補う強力なツール
受け取り時も年金形式なら公的年金等控除、一時金形式なら退職所得控除が適用され 税負担が抑えられます。
これらの税制優遇によりiDeCoは他の貯蓄や投資に比べ 効率的に資産を増やせる仕組みです。

iDeCoのメリットを公務員向けに徹底解説

iDeCoは、老後資金を貯めながら税金の負担を大幅に軽減できる非常に魅力的な制度です。
税制優遇の充実・運用の手軽さ・柔軟な運用オプションなど、他の貯蓄方法にはない独自の特徴が満載です。
| 項目 | 内容 |
| 税制優遇 | 掛け金全額所得控除、運用益非課税など |
| 運用の手軽さ | 自動引き落としで手間なく資産形成 |
| 公務員向け | 年金や退職金の不足を補える |
2024年12月から掛け金上限が月12000円から20000円に引き上げられ、より多くの資金を積み立てられるようになり節税効果もさらに拡大しています。
 ざくざく
ざくざく
これから紹介する3つのメリットを詳しくチェックして、iDeCoが自分のライフプランにどう役立つか考えてみましょう。
掛け金全額所得控除で税金が安くなる
iDeCoの最大の魅力は、毎月支払う掛け金が全額所得控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減される点です。
所得控除とは税金を計算する際の課税対象となる収入を減らせる仕組みです。
たとえば年収500万円の公務員が月12000円を拠出すると、年間で約28800円(税率20%の場合)の税金が安くなる計算です。
- 掛け金が全額所得控除
- 所得税や住民税が安くなる
- 2024年12月から上限引き上げ
他の貯蓄方法や投資では大幅な税制優遇を受けられるものはほとんどなく、iDeCoなら老後資金を貯めながら現在の手元資金を増やせる一石二鳥の制度と言えます。
2024年12月からの掛け金上限引き上げ(月20000円)により、たとえば年収600万円の方なら年間約48000円の節税が可能になり、30年間で約144万円の税金軽減が期待できます。
運用益が非課税で利益をフルに受け取れる
iDeCoで運用したお金の利益(運用益)は、税金がかからないため資産を効率的に増やせます。
通常は投資信託や株式で利益が出ると約20.315%の税金が引かれ、たとえば100万円の利益が出た場合は約20万円が税金として引かれ手元に残るのは約80万円です。
iDeCoならこの税金が免除されるため、長期的な資産形成で得られる利益が大幅に増える可能性があります。
- 通常の投資では約20%の税金がかかるがiDeCoなら全額受け取れる
- 非課税で利益が積み上がる
- 低リスクから高成長まで目標に合わせた商品選択が可能
低リスクの定期預金から成長を目指す全世界株式型の投資信託まで、自分の運用目標やライフプランに合ったスタイルを構築できます。
40歳からiDeCoを始めて60歳まで全世界株式型投資信託で運用した場合、年利5~7%で1000万円以上の資産を築ける可能性があります。
受け取り時も税制優遇でさらにお得
iDeCoで積み立てた資産を受け取る際も税制優遇が適用され、税負担を抑えながら老後資金を活用できます。
受け取り方法は「年金形式(分割)」と「一時金形式(一括)」の2種類があり、どちらを選んでも所得控除が受けられます。
年金形式では、公的年金等控除が適用され他の年金収入と合算しても税負担が軽減されます。
一時金形式では、退職所得控除が適用され退職金と同様の税制優遇を受けられます。
iDeCoは積み立て時と運用時と受け取り時の3つの段階で税制優遇があり、公務員の皆様が効率的に老後資金を準備できる仕組みです。
- 年金形式なら公的年金等控除、一時金なら退職所得控除が適用
- 受け取り時の税金が抑えられ老後資金を最大限活用
- 退職金と分離して受け取ることで控除枠を最大化
この3つの税制優遇は、他の投資や貯蓄方法では得られないiDeCoならではの強力なメリットです。
公務員のiDeCo利用者が急増している理由
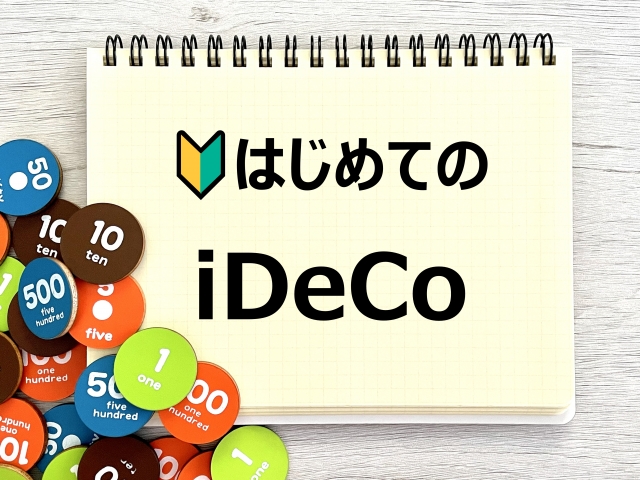
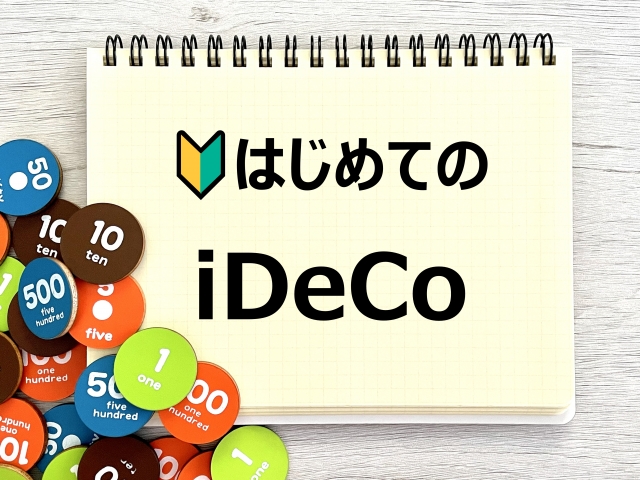
公務員のiDeCo利用者が急増している背景には、年金制度の変更と退職金の減少という2つの大きな理由があります。
老後資金計画に深刻な影響を与え、従来の公務員なら老後は安泰という認識を根本から覆しました。
2015年の年金制度改正や退職金の減額傾向により、公務員であっても自分で老後資金を準備することが不可欠になっています。
| 項目 | 内容 |
| 年金制度の変更 | 共済年金が厚生年金に統合など |
| 退職金の減少 | 40~100万円ほど減少 |
| iDeCoの必要性 | 年金や退職金だけでは老後資金が不足 |
老後2000万円問題・物価上昇・医療費や介護費の増加といった社会的な話題が老後資金への不安を広げiDeCoの必要性を一層高めています。
iDeCoはこれらの不安を軽減して将来の生活を経済的に安定させるための実践的な選択肢と言えるのではないでしょうか。
年金制度の改定で公務員の年金額が減少
日本の年金制度は3階建てと呼ばれ、1階は国民年金(20~60歳の全日本国民が加入)、2階は厚生年金(会社員や公務員が加入)、3階は企業年金(企業や団体が独自に運営)の構造になっています。
以前まで公務員は共済年金という独自の年金制度に加入しており、厚生年金より保険料が安く職域加算という上乗せ給付が老後の生活を支えていました。
しかしながら、2015年10月の年金制度改正で共済年金が厚生年金に統合され職域加算が廃止されました。
- 2015年の改正で共済年金が厚生年金に統合
- 職域加算廃止で年金受給額が約1割減
- 年金不足を補う資産形成の有効な手段
代わりに導入された年金払退職給付は支給額が職域加算より約1割少なく、全体として公務員の年金受給額が減少しています。
iDeCoは年金受給額の減少を補うための有効な手段として、加入者が急増する大きなきっかけとなっています。
退職金の減少で老後資金が不足
公務員の退職金も官民格差是正を目的とした政府の政策により継続的に減少傾向にあります。
たとえば地方公務員の場合だと、10年前と比べて退職金が200万円以上減少したケースも珍しくありません。
- 直近5年で約40万円減、10年前比で200万円以上の削減
- 減少傾向が続き依存が困難に
- 退職金不足を補う資産形成の手段として重要
この減少傾向は今後も続く見込みで、従来のように退職金を老後資金の柱とするのは難しくなっています。
iDeCoは老後資金の不足を補うための実践的な解決策として選ばれており、自分で資産を積み立てて老後の経済的な安定を確保できます。
iDeCoが注目される社会的背景
公務員のiDeCo利用者が急増している背景には、年金や退職金の減少に加え社会的な要因が大きく影響しています。
老後2000万円問題が2019年に金融庁の報告書で話題となり、公的年金だけでは老後の生活費が不足する可能性が広く知られるようになりました。
たとえば夫婦2人で老後30年間生活する場合、公的年金に加えて約2000万円の追加資金が必要と試算されています。
厚生労働省のデータによると、65歳以上の高齢者世帯の平均生活費は月約25万円とされており、今後さらに増えると予測されています。
- 公的年金だけでは生活費が不足
- 物価・医療費・介護費の増加で老後資金の必要性が増大
- 社会的不安を軽減し老後資金を賢く準備
物価の上昇や介護費の増加により老後の生活コストが年々上昇しており、自分で老後資金を準備する必要性が急激に高まっています。
iDeCoのデメリットと公務員が知っておくべき注意点
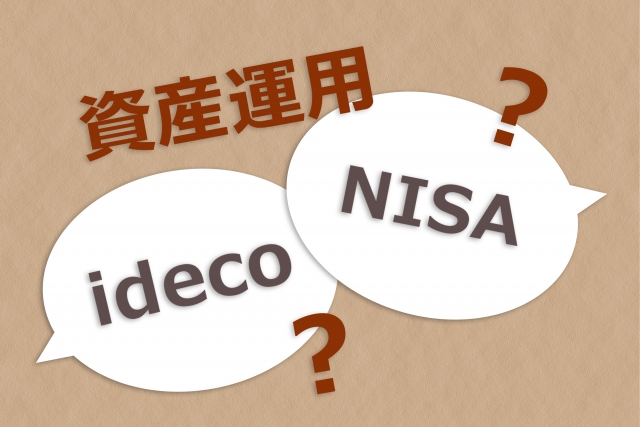
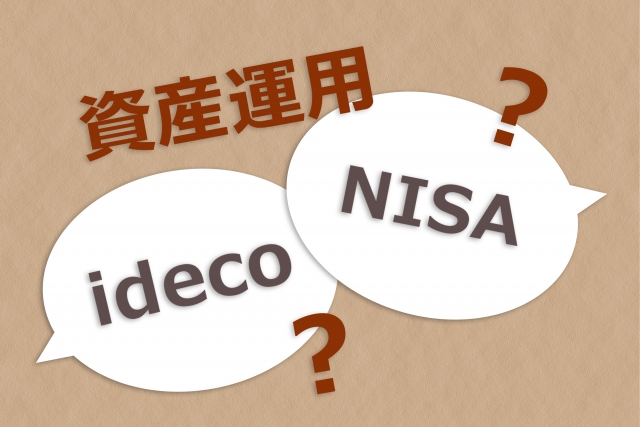
iDeCoには多くのメリットがありますがデメリットや注意点も存在します。
iDeCoは魅力的な制度ですが、資金の引き出し制限や掛け金の上限などいくつかの制約があることも事実です。



| 項目 | 内容 |
| 60歳まで引き出し不可 | 60歳まで資金ロック |
| 掛け金上限の低さ | 公務員は月20000円まで |
| 注意点 | 余裕資金かつ長期運用が前提 |
これらのデメリットを事前に知ることで、ライフプランに合った運用計画を立てて無理なく資産形成を進められます。
iDeCoを軸にしながら他の貯蓄や投資と組み合わせることで、老後資金の準備をより強固にできるかもしれません。
60歳まで資産を引き出せない制限
iDeCoの最大のデメリットは、原則として60歳になるまで積み立てた資産を引き出せないことです。
病気・住宅購入・子供の教育費などの急な出費が必要な場合でも、障害状態や死亡時を除きiDeCoの資金を使うことはできません。
この引き出し制限はiDeCoが老後資金の準備を目的とした長期的な制度であるためですが、資金計画に影響を与える重要なポイントです。
- 60歳まで資産はロックされ緊急時の利用は不可
- 生活資金や緊急資金を別で準備してiDeCoは老後専用に
- 家計に無理のない金額を設定して必要に応じて増額
たとえば40代でiDeCoを始めた場合だと20年近く資金がロックされるため、生活資金や緊急資金とは別に余裕資金を確保しておく必要があります。
無理に高額な掛け金を設定すると途中で家計が圧迫されるリスクがあるため、毎月の拠出額は慎重に決めるべきです。
公務員の掛け金上限が低い
2024年12月から公務員の掛け金上限が月額20000円に引き上げられました。
これにより節税効果や積み立て額が増えるためiDeCoの魅力がさらに高まっています。
それでも iDeCoだけで老後資金の全てを賄うのは難しい場合があり、他の貯蓄や投資との組み合わせを検討する必要があります。
たとえばNISAを併用することで 非課税で最大1800万円まで投資でき、iDeCoと組み合わせると老後資金の準備がより強固になります。


元本割れの可能性がある
投資信託など価格変動商品を選んだ場合は元本割れの可能性があります。
投資信託は株式や債券に投資するため、市場の変動により資産価値が下落し元本を下回る場合もあることを認識しておかなくてはいけません。
- 投資信託など価格変動商品は市場下落で元本割れの可能性あり
- 分散投資や低リスク商品で老後資金の元本割れリスクを軽減
- 長期運用で変動を吸収しネット証券の低コストの投資信託を活用
たとえば、世界的な経済危機や株価急落時に投資信託の価値が大幅に減少し、老後資金計画に影響を与えるリスクがあります。
元本割れリスクを理解して、自分のリスク許容度に合った商品選びと長期視点の運用で老後資金を安全に準備することが重要です。
証券会社の口座開設はポイントサイト経由がお得
証券会社の口座開設はハピタス経由がお得です。
ポイントサイトでは、特定の期間中に口座を開設すると追加の特典がもらえるキャンペーンが頻繁に行われています。
これにより、さらに多くのポイントや特典を得ることができます。
ポイントサイトを利用することで、通常の口座開設よりも多くのメリットを享受できるのでぜひ活用してみてください。
▼ハピタスの証券広告特集▼
 ざくざく
ざくざく
ハピタスに無料会員登録する方法
ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。
ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。
電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。
ハピタスに登録する手順は以下の3ステップです。
- ハピタスサイトを開く
- メールアドレスとパスワードを入力する
- 会員登録情報を入力する
まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。
▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼
上記バナーからの登録でキャンペーンポイントの獲得チャンスを得られます。
移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。
QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。
たとえQRコードを読み込んでも必要項目を入力する必要があります。
ハピタス会員登録のやり方は別ページで解説しています。


ハピタス登録のメリット・デメリット
ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイントが貯まりやすい
- 1ポイント1円で分かりやすい
- ポイント保証制度が充実している
- ポイント交換手数料が無料
- サイトが見やすく使いやすい
ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイント反映が遅い
- 会員ランクの昇格・維持が面倒
- コツコツ系コンテンツが少ない
- アプリ版ハピタスが使いにくい
- ポイント還元率は低い?
デメリットの部分は他のポイントサイトにも当てはまることがあるため、ハピタスのデメリット=ポイントサイト全体のデメリットと言える部分があります。
ハピタスでポイントを貯める方法
ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。
それらの広告を利用して、単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。
毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。
- ネットショッピング広告を利用する
- 無料体験系サービス広告を利用する
- リサイクル系広告を利用する
- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する
- 外食モニターコンテンツを利用する
- 友達紹介コンテンツを利用する
ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。
まとめ:公務員がiDeCoで老後資金を賢く準備
- 掛金全額所得控除・運用益非課税・受け取り時の控除で効率的な資産形成が可能
- 年金制度改正や退職金減少により老後資金の自己準備が不可欠
- 2024年12月から掛け金が月上限20000円に引き上げ
- 60歳まで引き出し不可
- 老後2000万円問題や生活コスト上昇でiDeCoの必要性が高まる
iDeCoは2001年にスタートし2017年から公務員も利用可能となった老後資金の準備に最適な制度です。
2015年の年金制度改正で共済年金が厚生年金に統合され、職域加算が廃止されたことで年金受給額が約1割減少しています。
老後2000万円問題が広く知られるようになり、公的年金だけでは老後の生活費が不足する可能性が指摘されています。



厚生労働省のデータによると、65歳以上の高齢者世帯の平均生活費は月約25万円・医療費は月約2万円で、介護費も含めると老後の生活コストが年々上昇しています。
iDeCoは掛け金の全額所得控除・運用益の非課税・受け取り時の税制優遇という3つのメリットで効率的に老後資金を貯められます。
▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼










