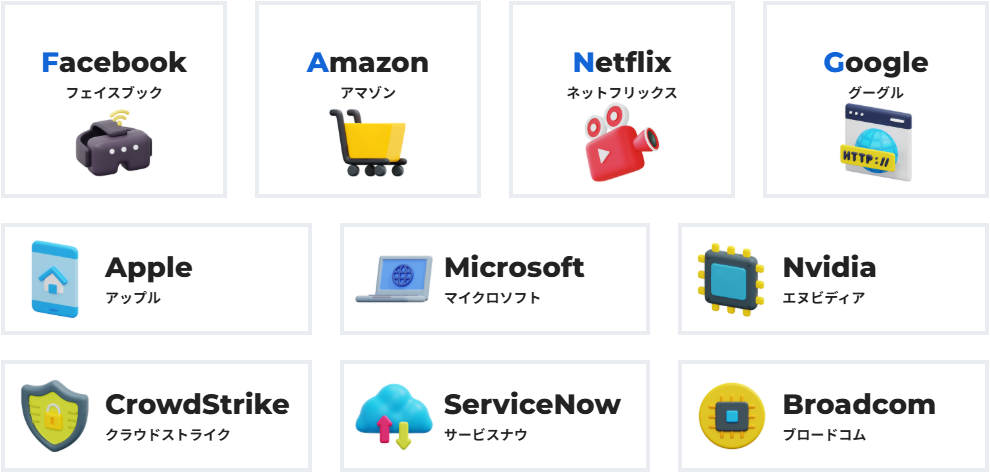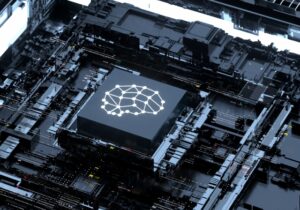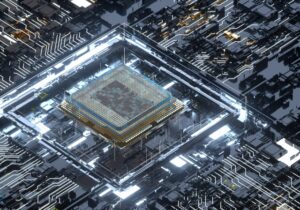FANG+(ファングプラス)に興味を持つ投資初心者から中級者、特に新NISAや積立投資信託を活用したい方は多いのではないでしょうか。
FANG+の基本・構成銘柄・最新の動向・ポートフォリオに組み入れるべき理由・リスク・他インデックスとの比較まで徹底的に解説します。
これからFANG+を活用した資産運用を検討している方に最新情報と実践的な知識を解説するので参考にしてください。
証券会社の口座開設をする際はポイントサイト経由がお得です。
▼ハピタスの証券広告特集▼
▼ハピタス登録はこちらからがお得
FANG+とは?ポートフォリオに組み込む前に基本構成を確認

FANG+は米国の主要テクノロジー企業を中心に構成された株価指数で、世界的な成長企業10社に均等配分で投資できるのが特徴です。
従来のS&P500やNASDAQ100と比べて攻めのポートフォリオとなっており、AI・クラウド・SNS・Eコマースなど今後の成長が期待される分野のリーダー企業が集まっています。
 ざくざく
ざくざく
FANG+はETFや投資信託を通じて手軽に投資が可能で、特に新NISAや積立投資との相性も抜群です。
FANG+の定義と対象となる構成銘柄
FANG+の「FANG」は、Facebook(現Meta)、Amazon、Netflix、Google(現Alphabet)の頭文字を取ったもので、これにApple・Microsoft・NVIDIAなどを加えた計10社で構成されています。
これらは米国を代表するテクノロジー・イノベーション企業であり世界経済を牽引する存在です。
出典:大和アセットマネジメント
各銘柄は均等比率で組み入れられており、特定の企業に偏りすぎない設計となっています。
この構成により成長性と分散性のバランスが取れたポートフォリオが実現します。
FANG+指数の特徴と運用方法
FANG+指数は構成銘柄10社を均等ウェイト(各10%前後)で組み入れるのが最大の特徴です。
これにより、特定の企業の株価変動リスクを抑えつつ全体として高い成長性を享受できます。
定期的にリバランス(組入比率の調整)が行われるため、常に最新の市場動向を反映したポートフォリオが維持されます。
ETFや投資信託を通じて少額からでも簡単に投資できる点も魅力で、長期積立や新NISA枠での活用が推奨されています。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 構成銘柄数 | 10社 |
| 組入比率 | 均等(各10%前後) |
| リバランス頻度 | 四半期ごと |
| 投資方法 | ETF・投資信託 |
FANG+ファンド・投資信託の選び方
FANG+に投資するにはETFや投資信託を活用するのが一般的です。
どちらかを選ぶ際は、信託報酬(運用コスト)・純資産残高・運用実績・分配金方針などを比較しましょう。
2024年からスタートしている新NISA対応商品を選ぶことで税制優遇を最大限活用できます。
- 信託報酬(コスト)の低さ
- 純資産残高の安定性
- 運用実績・リターン
- 新NISA対応か
- 分配金方針(再投資型・分配型)
国内では「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「iFreeETF FANG+」などが人気です。
自分の投資スタイルやリスク許容度に合わせて最適な商品を選びましょう。


FANG+構成銘柄の最新動向と入れ替えルール(2024年・2025年基準)
FANG+の構成銘柄は、時代の変化や企業の成長性に応じて見直されることがあります。
2024年・2025年基準では、AI・クラウド・EV(電気自動車)分野の成長企業が注目されており、既存のGAFAMに加えNVIDIAなどの新興リーダーも含まれています。



中国のAlibabaやBaiduもグローバルなテック企業として組み入れられていましたが、2025年時点では米国の企業に統一されています。
FANG+構成銘柄の過去から最新までの変遷
FANG+は2017年に誕生して以来、構成銘柄の一部が入れ替わってきました。
当初はFacebook・Amazon・Netflix・Google(Alphabet)・Apple・Microsoft・Tesla・NVIDIA・Alibaba・Baiduの10社が中心でしたが、企業の成長や業績、時価総額の変動により組入比率や銘柄の入れ替えが行われています。
- 2017年:FANG+指数誕生
- 2020年:TeslaやNVIDIAの比率上昇
- 2023年:AI関連銘柄の注目度アップ
- 2024年:構成銘柄の見直し検討
特に2023年以降はAI分野の急成長を受けてNVIDIAの存在感が増し、今後も新たなテクノロジー企業が加わる可能性があります。
銘柄入れ替えはいつ?基準・タイミング・固定銘柄の詳細
FANG+の銘柄入れ替えは、四半期ごとに実施されるリバランスのタイミングで検討されます。
入れ替え基準は、時価総額・流動性・成長性・業績などが重視され、テクノロジー分野で世界的な影響力を持つ企業が選定されます。
一部の銘柄(GAFAMなど)は固定的に組み入れられる傾向が強いですが、市場環境や企業の業績悪化などがあれば入れ替え対象となることもあります。
この柔軟なルールがFANG+の成長性を支えています。
| 入れ替えタイミング | 基準 | 固定銘柄 |
|---|---|---|
| 四半期ごと | 時価総額・成長性・流動性 | GAFAM中心 |
構成銘柄入れ替えによるパフォーマンスやリスクへの影響
構成銘柄の入れ替えはFANG+のパフォーマンスやリスクに大きな影響を与えます。
成長著しい企業を新たに組み入れることで指数全体のリターン向上が期待できますが、一方で新興企業のボラティリティ(価格変動)が高まるリスクもあります。
- 成長企業の組入でリターン向上
- 新興企業のボラティリティ増加
- 業績悪化銘柄の除外でリスク低減
既存銘柄の業績悪化による入れ替えは短期的なパフォーマンス低下を招くこともあります。
このため、FANG+は高リターンを狙いつつもリスク管理が重要なインデックスと言えるでしょう。
FANG+をポートフォリオに加える最新理由5選
FANG+をポートフォリオに加えるべき理由は、AI・テクノロジー主導の成長性・米国企業の実績・分散投資効果・優れた運用実績などがあります。
新NISAや積立投資信託での活用メリット、そして将来の資産形成に有効な点など多岐にわたります。



ここからは、FANG+をポートフォリオに加える最新の5つの理由を詳しく解説します。
AI・テクノロジー主導の成長性と米国企業の実績
FANG+の最大の魅力は、AI・クラウド・デジタル広告・EVなど、今後も成長が期待される分野のリーダー企業に投資できる点です。
米国のテクノロジー企業は世界経済のイノベーションを牽引しており、過去10年で圧倒的な実績を残しています。
- AI・クラウド・EV分野のリーダー企業
- 米国テック企業の圧倒的な実績
- グローバル市場での競争力
これらの企業は、グローバル市場での競争力や収益性も高く今後も持続的な成長が見込まれます。
NASDAQやNYSE上場との連動による分散投資効果
FANG+の構成銘柄は、NASDAQやNYSEといった米国の主要証券取引所に上場しており、業種や事業領域も多岐にわたります。
これにより、単一企業への集中リスクを抑えつつテクノロジー分野全体の成長を享受できます。
- NASDAQ・NYSE上場の多様な企業
- 業種・事業領域の分散
- 他インデックスとの組み合わせで安定化
米国市場のダイナミズムを活かした分散投資が可能で、他のインデックスと組み合わせることで安定したポートフォリオ構築が実現します。


指数の運用実績とリターンの時系列データ比較
FANG+指数は、過去数年間で他の主要インデックスを上回るリターンを記録しています。
特に2020年以降、AI・クラウド・EV分野の成長が加速しFANG+構成銘柄の株価が大きく上昇しました。
時系列データで見ると、S&P500やNASDAQ100と比較しても高いパフォーマンスを維持しており、長期投資家にとって魅力的な選択肢となっています。
| 年 | FANG+リターン | S&P500リターン | NASDAQ100リターン |
|---|---|---|---|
| 2020 | +103.5% | +16.3% | +47.6% |
| 2021 | +19.6% | +26.9% | +27.5% |
| 2022 | -39.1% | -19.4% | -32.6% |
| 2023 | +74.2% | +24.2% | +53.8% |
NISA・積立投資信託での活用メリット
FANG+は新NISAの対象商品としても近年人気が高まっています。
信託報酬が比較的低く、長期で積み立てることで複利効果を最大限に活かせる点が魅力です。
- 運用益・分配金が非課税
- 少額から積立可能
- 長期投資で複利効果を享受
新NISA口座を利用することで、運用益や分配金が非課税となり資産形成の効率が大幅に向上します。
出典:金融庁
新NISAは少額からでも始められるため投資初心者にもおすすめです。
将来の資産形成に有効な理由とシミュレーション結果
FANG+は、今後も成長が期待されるテクノロジー分野のリーダー企業に分散投資できるため、将来の資産形成に非常に有効です。
過去の実績をもとに毎月1万円を10年間積み立てた場合のシミュレーションを行うと、年平均リターンが15~20%の場合、元本1200万円が約2700~3700万円に増える可能性があります。
ただし、相場の変動や下落局面では元本割れのリスクもあるため、過去の利回りだけで判断せずリスクも十分に考慮しましょう。
| 積立額(月額) | 期間 | 年平均リターン | 最終評価額(概算) |
|---|---|---|---|
| 1万円 | 10年 | 15% | 約2700万円 |
| 1万円 | 10年 | 20% | 約3700万円 |
過去の高いリターンを考慮すればさらに大きな資産形成も期待できますが、リスクもあるため分散投資や長期運用が重要です。
FANG+をポートフォリオに組み込む際の注意点とリスク
FANG+は高い成長性とリターンが期待できる一方で損失リスクも無視できません。
特に市場急変時の価格変動や構成銘柄の業績悪化、為替リスクなどに注意が必要です。



ここからはFANG+投資の主なリスクと注意点を解説するので、FANG+に興味がある方はチェックしておきましょう。
市場急変時のリスクとパフォーマンスの変動
FANG+はテクノロジー分野に特化しているため、市場全体が不安定な時やITバブル崩壊のような局面では大きな下落リスクがあります。
2022年のように、金利上昇や景気後退懸念が強まると構成銘柄の株価が急落することもあります。
- テクノロジー株特有のボラティリティ
- 市場急変時の大幅下落リスク
- 長期運用でリスク分散
短期的な値動きに一喜一憂せず長期視点での運用が重要です。


費用・信託報酬・負担コストの比較ポイント
FANG+関連のETFや投資信託は、商品ごとに信託報酬や運用コストが異なります。
信託報酬が高いと長期的なリターンに大きく影響するため、できるだけ低コストの商品を選ぶことが大切です。
為替手数料や売買手数料などの隠れコストにも注意しましょう。
コスト比較は投資成果を左右する重要なポイントです。
| 商品名 | 信託報酬 | その他コスト |
|---|---|---|
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 0.7755% | 為替手数料等 |
| iFreeETF FANG+ (316A) | 0.6050% | 売買手数料等 |
FANG+ポートフォリオ特有のリスクとリターンの相関
FANG+は高リターンを狙える一方で、構成銘柄がテクノロジー分野に集中しているため業界全体の不調が指数全体に大きく影響します。
個別銘柄の業績悪化や規制強化など特有のリスクも存在します。
- テクノロジー分野への集中リスク
- 個別銘柄の業績・規制リスク
- 分散投資でリスク低減
リターンとリスクのバランスを理解し、他の資産クラスと組み合わせて分散投資を心がけましょう。
他のインデックス・ファンドとのパフォーマンス比較
FANG+は高い成長性を誇る一方で、他の代表的なインデックス(S&P500やNASDAQ100など)と比較してどのような違いがあるのかも重要なポイントです。
パフォーマンス・リスク・リターンの観点から、FANG+と他インデックスの特徴を比較することで自分の投資スタイルに合った選択がしやすくなります。



ここからは、時系列データや数値データを用いてFANG+と他インデックスの違いを詳しく解説します。
代表的なインデックス(S&P500やNASDAQ100など)との時系列比較
FANG+はS&P500やNASDAQ100と比べて構成銘柄が少なく、より攻めのポートフォリオとなっています。
そのため、上昇局面では大きなリターンを狙えますが下落局面では値動きが激しくなる傾向があります。
時系列で比較すると、FANG+は2020年や2023年のようなテクノロジー株が強い年に大きくアウトパフォームしていますが、2022年のような調整局面では大きく下落しています。
このように、FANG+はハイリスク・ハイリターン型のインデックスと言えるでしょう。
| 年 | FANG+リターン | S&P500リターン | NASDAQ100リターン |
|---|---|---|---|
| 2020 | +103.5% | +16.3% | +47.6% |
| 2021 | +19.6% | +26.9% | +27.5% |
| 2022 | -39.1% | -19.4% | -32.6% |
| 2023 | +74.2% | +24.2% | +53.8% |
パフォーマンス・リスク・リターンの数値データで見る違い
FANG+は他のインデックスと比べてリターンが高い一方で、リスク(標準偏差)も大きいのが特徴です。
シャープレシオ(リスクあたりのリターン)で見ると、好調な年は非常に高い数値を記録しますが調整局面では大きく低下します。
S&P500やNASDAQ100は構成銘柄が多く値動きが比較的安定しています。
自分のリスク許容度や投資目的に応じて、FANG+と他インデックスを組み合わせるのも有効な戦略です。
| インデックス | 年平均リターン(5年) | 標準偏差 | シャープレシオ |
|---|---|---|---|
| FANG+ | 約30% | 約35% | 約0.85 |
| S&P500 | 約12% | 約18% | 約0.67 |
| NASDAQ100 | 約18% | 約22% | 約0.82 |
FANG+ポートフォリオの今後と2025年以降の展望
2025年以降も、AI・クラウド・EVなどの分野で新たなリーダー企業が登場する可能性が高く、FANG+の構成銘柄も時代に合わせて進化していくでしょう。
今後は米国だけでなくグローバルなテクノロジー企業の組み入れも検討されるかもしれません。
- AI・テクノロジー分野の成長継続
- 新興企業の組み入れ可能性
- グローバル分散の強化
投資家は定期的に構成銘柄や市場動向をチェックし、柔軟にポートフォリオを見直すことが大切です。
投資信託・ETF・個別株組入の判断ポイント
FANG+に投資する方法は投資信託・ETF・個別株の3つが主流です。
投資信託やETFは分散投資と低コストが魅力で初心者にもおすすめです。
個別株は自分で銘柄を選びたい上級者向けですがリスク管理が難しくなります。
- 投資信託・ETF:分散投資・低コスト・初心者向け
- 個別株:自分で選定・高リスク高リターン・上級者向け
- 運用コストやNISA対応も要チェック
自分の投資スタイルやリスク許容度、運用コストを比較して最適な方法を選びましょう。
【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ


ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。
ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。
電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。
ハピタスに登録する手順は以下の通りです。
- ハピタス登録の紹介リンクを押す
- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ
- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力
- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力
- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力
- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要
- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要
- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要
- 登録完了
まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。
▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼
 ざくざく
ざくざく
移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。
QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。
▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼


ハピタス登録のメリット・デメリット|ポイ活初心者必見
ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイントが貯まりやすい
- 1ポイント1円で分かりやすい
- ポイント保証制度が充実している
- ポイント交換手数料が無料
- サイトが見やすく使いやすい
ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイント反映が遅い
- 会員ランクの昇格・維持が面倒
- コツコツ系コンテンツが少ない
- アプリ版ハピタスが使いにくい
- ポイント還元率は低い?
デメリットの部分は他のポイントサイトにも当てはまることがあるため、ハピタスのデメリット=ポイントサイト全体のデメリットと言える部分があります。
ハピタスで効率的にポイントを貯める方法|初心者でも簡単
ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。
それらの広告を利用して単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。
毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。
- ネットショッピング広告を利用する
- 無料体験系サービス広告を利用する
- リサイクル系広告を利用する
- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する
- 外食モニターコンテンツを利用する
- 友達紹介コンテンツを利用する
ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。
ハピタスのポイント失効に注意
貯めたポイントは1ポイント残らず使い切ることで意味があるものになります。
ハピタスのポイント有効期限は以下の通りです。
第10条(当サイトのサービス制限及び承認抹消)
1.会員が以下の各号に掲げる事項に該当した場合、弊社は第2項に定める措置をとることができるものとします。
H. 180日以上当サイトへのログインがない場合。
V. 最後にポイント獲得した日から180日が経過した場合。
一定期間ログインしなかったりポイントを獲得しない状態が続くと、獲得ポイントが失効してしまうので注意しましょう。


FANG+をポートフォリオに入れるべき理由まとめ
- 2017年:約30~40%
- 2018年:約0~10%
- 2019年:約30~40%
- 2020年:約50~60%
- 2021年:約20~30%
- 2022年:約-20~-30%
- 2023年:約60~70%
- 2024年:約10~15%
FANG+は、AIやテクノロジー分野の成長企業に集中投資できる現代の資産運用に最適なインデックスです。
高いリターンを狙える一方でリスクも大きいため、長期運用や分散投資を意識することが重要です。



今後もテクノロジー分野の成長が続く限りFANG+は魅力的な投資先となるでしょう。
▼ハピタス登録はこちらからがお得▼