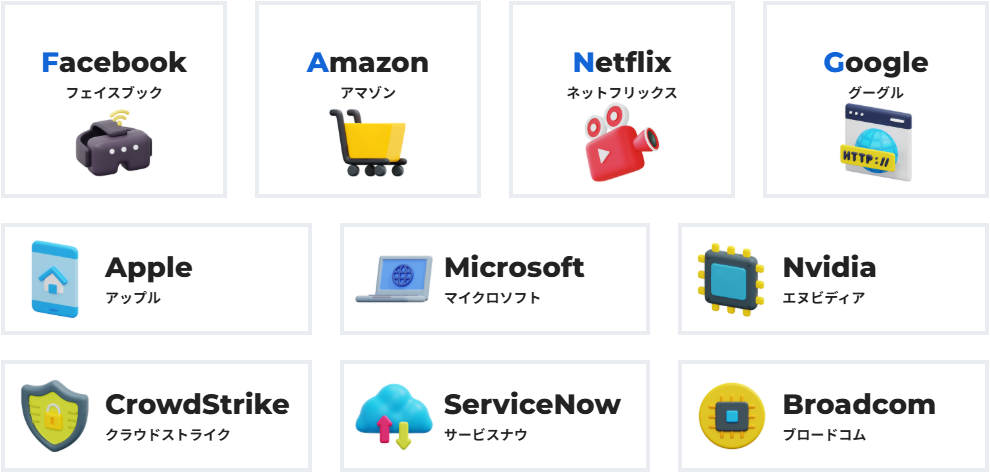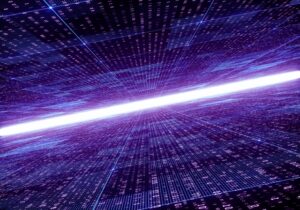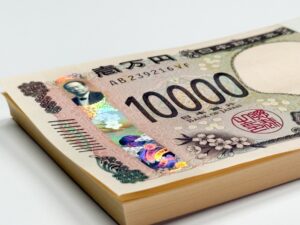FANG+とNASDAQ100のどちらに投資すべきか迷っている初心者の方は多いのではないでしょうか。
このページでは「FANG+とNASDAQ100どっちがいいの?」という疑問を持つ方が納得して投資を始められるようわかりやすくまとめました。
違い・特徴・パフォーマンス・リスク・投資信託やETFの選び方まで徹底的に解説し、最適な選択肢を見つけるお手伝いをします。
 ざくざく
ざくざく
▼ハピタス登録はこちらからがお得▼
▼ハピタスの証券広告特集▼
FANG+とNASDAQ100の違いを徹底比較【初心者視点で解説】


FANG+とNASDAQ100は、どちらも米国の成長企業に投資できる人気の株価指数ですが、その構成やリスクやリターンには大きな違いがあります。
FANG+はわずか10銘柄に集中投資する超攻撃型インデックスで、主にGAFAMやテック大手を中心に構成されています。
NASDAQ100は100銘柄以上に分散されており、テクノロジー以外のセクターも一部含まれます。



| 項目 | FANG+ | NASDAQ100 |
|---|---|---|
| 構成銘柄数 | 10 | 約100 |
| 主な業種 | テクノロジー中心 | テクノロジー中心+他業種 |
| リスク | 高い | やや高い |
| リターン | 非常に高い時期も | 安定して高い |
FANG+インデックスとは?特徴や対象銘柄・指数の概要
FANG+インデックスは、米国の代表的なテクノロジー企業や成長株10社で構成される株価指数です。
FANGはFacebook(現Meta)・Amazon・Netflix・Google(現Alphabet)の頭文字ですが、実際にはApple・NVIDIA・Microsoftなども含まれています。
- 構成銘柄は10社のみ
- GAFAMやNVIDIAなど米国テック大手が中心
- 値動きが大きくリターンも大きい
- 分散性は低いが成長性は抜群
この指数は少数精鋭の超大型グロース株に集中投資するため、値動きが大きく短期間で高リターンを狙える一方、下落時のリスクも高いのが特徴です。
出典:大和アセットマネジメント
近年はAI・クラウド・半導体分野の成長を背景にFANG+のパフォーマンスが注目されています。
NASDAQ100とは?構成企業やセクター・株価指数の基本
NASDAQ100は、米国NASDAQ市場に上場する時価総額上位約100社(金融を除く)で構成される株価指数です。
テクノロジー企業が多いものの、ヘルスケアや消費財など他セクターも一部含まれています。
- 構成銘柄は約100社
- テクノロジー中心だが他業種も含む
- 分散性が高く、リスクがやや低い
- 長期投資に向いている
GAFAMやNVIDIAなどFANG+と重複する銘柄も多いですが、より分散されたポートフォリオとなっているためリスクが比較的抑えられています。
長期的に安定した成長を目指す投資家に人気がありETFや投資信託も豊富です。
S&P500・FANG+・NASDAQ100の違いも押さえよう
FANG+とNASDAQ100だけでなくS&P500も米国株投資の代表的な指数です。
S&P500は米国の大型株500社で構成され、テクノロジー以外の幅広い業種をカバーしています。
FANG+は超集中型、NASDAQ100はテック中心の分散型、S&P500は米国全体の分散型という違いがあります。
リスク・リターン・分散性のバランスを考える上で、これら3つの違いを理解しておくことが重要です。
| 指数名 | 構成銘柄数 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| FANG+ | 10 | テック大手集中・高リスク高リターン |
| NASDAQ100 | 約100 | テック中心・分散性あり |
| S&P500 | 500 | 米国全体・分散性最強 |
FANG+とNASDAQ100「どっちが初心者におすすめ?」を先に結論!
FANG+とNASDAQ100のどちらが初心者におすすめか先に結論をお伝えします。
結論としては、分散性やリスク管理の観点からNASDAQ100の方が初心者にはおすすめです。
FANG+はリターンが大きい反面、値動きが激しく短期的な下落リスクも高いため、投資経験が浅い方にはややハードルが高いと言えます。
NASDAQ100は100社以上に分散されており、長期的な成長も期待できるため安心して積立投資を始めたい方に向いています。



結論:投資初心者にはどちらが向いているのか
投資初心者にとっては、リスクを抑えつつ安定した成長を目指せるNASDAQ100がより適しています。
FANG+は少数精鋭の成長株に集中投資するため、短期間で大きなリターンを狙える一方、下落時のダメージも大きくなりがちです。
- リスク分散を重視するならNASDAQ100
- 短期で大きなリターンを狙いたいならFANG+
- 長期・積立投資にはNASDAQ100が無難
NASDAQ100は100社以上に分散されているため、個別銘柄の影響を受けにくく長期的な資産形成に向いています。
特に積立投資や長期保有を考えている初心者には、NASDAQ100の方が安心して始めやすいでしょう。
それぞれが選ばれる理由と投資家の評判・口コミ
FANG+は「成長性が圧倒的」「AIやテックの波に乗りたい」という理由で選ばれることが多いです。
NASDAQ100は「分散性が高く安心」「長期で安定したリターンが期待できる」といった声が目立ちます。
- FANG+:ハイリスク・ハイリターンを求める人に人気
- NASDAQ100:安定成長・分散投資を重視する人に人気
実際の口コミでも、FANG+は値動きの大きさに驚く声や短期で大きく増えた・減ったという体験談が多いです。
NASDAQ100は「コツコツ積立で資産が増えた」「暴落時も比較的安心できた」といった評価が多く、初心者や長期投資家に支持されています。
FANG+はおすすめしない?
FANG+は魅力的なリターンが期待できる一方で「おすすめしない」と言われる理由がいくつか存在します。
銘柄の偏りや分散投資のリスク、手数料や信託報酬などのコスト、米国テック株特有の変動リスク、為替リスク、NISAでの注意点などが挙げられます。
- 銘柄の偏りや分散投資のリスク
- 手数料や信託報酬などのコスト
- 米国テック株特有の変動リスク
- 為替リスク
- NISAでの注意点
これらの落とし穴を理解せずに投資を始めると思わぬ損失を被る可能性もあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
ETF・投資信託で選ぶ!各商品の特徴と選び方
FANG+やNASDAQ100に投資する方法はETF・投資信託などさまざまです。
それぞれの商品には手数料・取引のしやすさ・積立対応の有無など特徴があるので、自分の投資スタイルや目的に合わせて最適な商品を選ぶことが大切です。



ここからは代表的なファンドやETFの特徴・費用・人気の理由を詳しく解説します。
ifreenext fang+インデックスの特徴・費用・人気
「ifreenext fang+インデックス」はFANG+指数に連動する日本の投資信託です。
少額から積立投資ができ、NISAやiDeCoにも対応しているため初心者にも人気があります。
- FANG+指数に連動
- 少額から積立可能
- NISA・iDeCo対応
- 信託報酬はやや高め
信託報酬は年0.7755%(税込)とやや高めですが、FANG+の成長性を手軽に享受できる点が魅力です。
ただし、値動きが大きいため長期で積立投資をする場合もリスク許容度を考えて運用しましょう。
NASDAQ100系ETF(QQQなど)の取引・信託報酬・リスク
NASDAQ100に連動する代表的なETFは「QQQ」や「iFreeNEXT NASDAQ100インデックス」などがあります。
QQQは米国市場で取引されており信託報酬は年0.2%程度と低コストです。日本の証券会社でも購入でき流動性が高く分配金も受け取れます。
- QQQは低コストで人気
- 分散性が高く、リスクが抑えられる
- 為替リスク・税制に注意
値動きはFANG+よりマイルドで長期投資や積立に向いていますが、為替リスクや米国株特有の税制にも注意が必要です。
その他のファンド比較(つみたて・一般口座・楽天証券など)
FANG+やNASDAQ100に投資できるファンドは、楽天証券・SBI証券・マネックス証券など主要ネット証券で取り扱いがあります。
つみたてNISA対応商品や一般口座での一括投資も可能です。信託報酬・最低投資額・積立設定のしやすさなどを比較して自分に合った商品を選びましょう。
証券会社ごとにキャンペーンやポイント還元も異なるため、口座開設前にチェックするのがおすすめです。
証券会社の口座開設方法は別ページで解説しているので参考にしてください。
▼SBI証券口座の開設方法はこちらからどうぞ▼


▼楽天証券口座の開設方法はこちらからどうぞ▼


| 証券会社 | 主な取扱商品 | 特徴 |
|---|---|---|
| 楽天証券 | ifreenext fang+、NASDAQ100系ETF | ポイント投資・積立設定が簡単 |
| SBI証券 | ifreenext fang+、QQQ | 手数料が安い・商品数が豊富 |
| マネックス証券 | ifreenext fang+、NASDAQ100系ETF | 米国株に強い・ツールが充実 |
FANG+インデックス・NASDAQ100のパフォーマンス推移と今後の成長性
FANG+インデックスとNASDAQ100は、どちらも過去数年で高いパフォーマンスを記録していますが、その値動きや成長性には違いがあります。
FANG+は特定のテック大手に集中しているため、好調な時期は爆発的なリターンを生み出しますが、逆に下落局面では大きなマイナスとなることもあります。
NASDAQ100はFANG+と比べて分散性が高く、これまで安定した成長を続けてきています。



今後もAI・クラウド・半導体などの分野が成長を牽引する見通しですが、構成銘柄や市場環境の変化にも注意が必要です。
過去の値動き・株価推移データを比較(直近数年の推移)
直近5年のリターンを比較すると、FANG+はNASDAQ100を大きく上回る年もありました。
たとえば、2020年から2023年にかけてはFANG+がAI・クラウドブームで急騰し、NASDAQ100よりも高いパフォーマンスを記録しました。
しかし、2022年のようなテック株全体の調整局面では、FANG+の下落幅がNASDAQ100よりも大きくなる傾向があります。
このように、FANG+は値動きが激しくNASDAQ100は比較的安定しているのが特徴です。
| 年 | FANG+リターン | NASDAQ100リターン |
|---|---|---|
| 2020 | +80% | +48% |
| 2021 | +30% | +27% |
| 2022 | -40% | -33% |
| 2023 | +60% | +45% |
今後の収益・見通し・注目ポイント
今後の見通しとしては、AI・半導体・クラウド分野の成長がFANG+とNASDAQ100の両方に追い風となるでしょう。
特にFANG+は、構成銘柄のイノベーションが続く限り高い成長が期待できますが、個別企業の業績悪化が指数全体に大きく影響するリスクもあります。
NASDAQ100は分散性が高いため、安定した成長を目指す投資家に引き続き支持されるでしょう。
- AI・半導体・クラウド分野の成長がカギ
- FANG+は個別銘柄の影響が大きい
- NASDAQ100は分散性で安定感あり
どちらも米国経済やテクノロジー業界の動向に注目が必要です。
銘柄入れ替え・構成変動のリスク
FANG+やNASDAQ100は、定期的に構成銘柄の入れ替えが行われています。
特にFANG+は10銘柄と少数精鋭のため、1社の入れ替えや業績悪化が指数全体に大きな影響を与えるリスクがあります。
- FANG+は1社の影響が大きい
- NASDAQ100は分散でリスクが分散される
- 定期的な銘柄入れ替えに注意
NASDAQ100も入れ替えはありますが銘柄数が多いため影響は限定的です。
どちらかに投資する際は構成銘柄の変動や業界トレンドの変化にも注意しましょう。
FANG+・NASDAQ100投資のメリット・デメリットと注意点
FANG+とNASDAQ100にはそれぞれ異なるメリット・デメリットがあります。
FANG+は高い成長性とリターンが魅力ですが、リスクも大きく投資するのは「やめとけ」と言われることも。
NASDAQ100は分散性と安定感があり、長期投資に向いていますがリターンがFANG+ほど爆発的ではありません。



FANG+のメリット・デメリット(やめとけと言われる理由も)
FANG+の最大のメリットは、米国を代表するテック大手の成長をダイレクトに享受できる点です。
AI・クラウド・半導体などの分野で世界をリードする企業が多く、過去には圧倒的なリターンを記録しました。
- メリット:高成長・高リターンが狙える
- メリット:米国テック大手の成長を享受
- デメリット:値動きが激しくリスクが高い
- デメリット:分散性が低い
一方で、10銘柄に集中投資するため個別企業の業績悪化や市場の逆風が指数全体に大きく影響します。
このリスクの高さから「FANG+はやめとけ」と言われることもあり、短期的な値動きに耐えられない人や分散投資を重視する人には向きません。
NASDAQ100のメリット・デメリット(リスクや費用面)
NASDAQ100のメリットは、100社以上に分散投資できるため個別銘柄の影響を受けにくく、安定した成長が期待できる点です。
ETFや投資信託の選択肢が豊富で信託報酬も比較的低コストです。
- メリット:分散性が高くリスクが抑えられる
- メリット:低コストで投資可能
- デメリット:リターンはFANG+ほど高くない
- デメリット:テック不調時は下落リスクあり
デメリットとしては、FANG+ほどの爆発的なリターンは狙いにくくテックセクターの比率が高いため、業界全体の不調時には大きく下落するリスクがあることです。
それでも長期・積立投資には非常に適した選択肢と言えるでしょう。


テックセクター中心投資のリスクと分散の考え方
FANG+もNASDAQ100もテックセクターの比率が高いため、業界全体の不調時には大きな下落リスクがあります。
特にFANG+は10銘柄に集中しているため分散効果が弱くリスクが高まります。
- テックセクターの不調時は大きく下落する可能性
- 分散投資でリスクを抑えることが重要
- 他のインデックスとの組み合わせも有効
NASDAQ100は100社以上に分散されているもののテック依存度が高い点は共通です。
リスクを抑えたい場合は、S&P500や全世界株式インデックスなどより幅広い分散投資も検討しましょう。
FANG+・NASDAQ100の投資はどんな人におすすめ?やめた方がいい人は?


FANG+やNASDAQ100は、成長性を重視する投資家や米国テック企業の将来性に期待する人におすすめです。
値動きの大きさに不安を感じる人や短期的な下落に耐えられない人には向きません。



自分のリスク許容度や投資目的を明確にして、無理のない範囲で投資を始めることが大切です。
おすすめしない人・初心者が陥りがちな失敗例
FANG+やNASDAQ100は、短期的な値動きが大きいため下落局面で慌てて売却してしまう初心者が多いです。
FANG+のような集中投資型は、リスク許容度が低い人や分散投資の重要性を理解していない人にはおすすめできません。
- 短期の値動きに一喜一憂しやすい人
- リスク許容度が低い人
- 分散投資を重視したい人
「話題だから」「過去のリターンが高いから」と安易に飛びつくのではなく、自分の投資スタイルに合っているかをしっかり考えましょう。
長期・積立・つみたて投資で向いている人
NASDAQ100は長期・積立・つみたて投資に非常に向いています。
コツコツと積み立てることで、短期的な値動きに左右されず時間を味方につけて資産を増やすことができます。
FANG+も長期で成長を期待する人には魅力的ですが、リスクが高いため資産の一部でチャレンジするのが賢明です。
- 長期で資産形成を目指す人
- 積立投資をコツコツ続けられる人
- 米国テックの成長を信じる人
長期目線で米国テックの成長を信じる人には、FANG+とNASDAQ100どちらも選択肢になります。
FANG+とNASDAQ100以外の選択肢(世界インデックス・S&P500など)
リスク分散や安定性を重視するなら、S&P500や全世界株式インデックス(オルカンなど)も有力な選択肢です。
全世界株式インデックス(オルカンなど)は、米国だけでなく世界中の企業に分散投資できるため、特定セクターや地域のリスクを抑えられます。
- S&P500:米国全体に分散投資
- 全世界株式:世界中の企業に分散投資
- リスク分散を重視する人におすすめ
FANG+やNASDAQ100と組み合わせてバランスの良いポートフォリオを作るのもおすすめです。


どこで買える?証券会社・口座開設・取引の流れ
FANG+やNASDAQ100に連動する投資信託やETFは、主要なネット証券会社で簡単に購入できます。
口座開設から取引までの流れはシンプルでスマホやパソコンから手続きが可能です。
証券会社ごとに取扱商品・手数料・ポイント還元などのサービスが異なるため、比較して自分に合った証券会社を選びましょう。



積立設定やNISA口座の利用もできるので初心者でも安心して始められます。
楽天証券・マネックス証券・主要証券会社を比較
楽天証券・SBI証券・マネックス証券などの大手ネット証券では、FANG+やNASDAQ100に連動する投資信託やETFが豊富に揃っています。
楽天証券はポイント投資や積立設定が簡単で楽天ポイントが貯まるのが魅力です。
SBI証券は手数料が安く商品ラインナップが豊富。
マネックス証券は米国株の取扱いが強みでツールも充実しています。
自分の投資スタイルや重視するサービスでメインで利用する証券会社を選ぶのがおすすめです。
| 証券会社 | 特徴 | 主な取扱商品 |
|---|---|---|
| 楽天証券 | ポイント投資・積立が簡単 | ifreenext fang+、NASDAQ100系ETF |
| SBI証券 | 手数料が安い・商品数豊富 | ifreenext fang+、QQQ |
| マネックス証券 | 米国株に強い・ツール充実 | ifreenext fang+、NASDAQ100系ETF |
必要な元本・運用コスト・信託報酬・手数料まとめ
FANG+やNASDAQ100の投資信託は、100円から積立可能な商品も多く少額から始められます。
ETFの場合は1口数万円程度から購入できますが、為替手数料や売買手数料がかかる場合もあります。
信託報酬はFANG+で年0.77%前後・NASDAQ100系ETFは0.2%前後と、それぞれの商品によって運用コストに差があります。
- 投資信託は100円から積立可能
- ETFは1口数万円から購入可能
- 信託報酬・手数料は商品ごとに異なる
長期投資では運用コストがリターンに大きく影響するため、取引前に手数料や信託報酬をしっかり比較しましょう。
積立設定・取引方法のポイント
投資信託の積立投資をする場合は、証券会社の自動積立サービスを活用すると便利です。
毎月一定額を自動で投資できるため、相場のタイミングを気にせず長期で資産形成が可能です。
NISAやつみたてNISAを利用すれば運用益が非課税になるメリットもあります。
- 自動積立サービスを活用
- NISA・つみたてNISAの非課税枠を利用
- ETFは取引時間・為替にも注意
ETFの場合は、取引時間や為替レートにも注意しながら定期的に買い増す方法もおすすめです。
【登録・準備編】ハピタスの始め方と会員登録の流れ
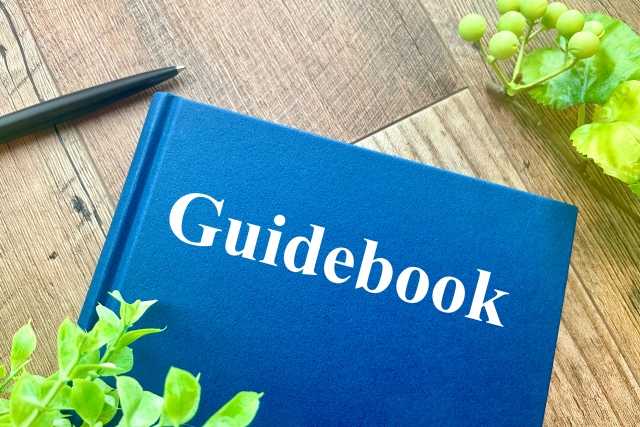
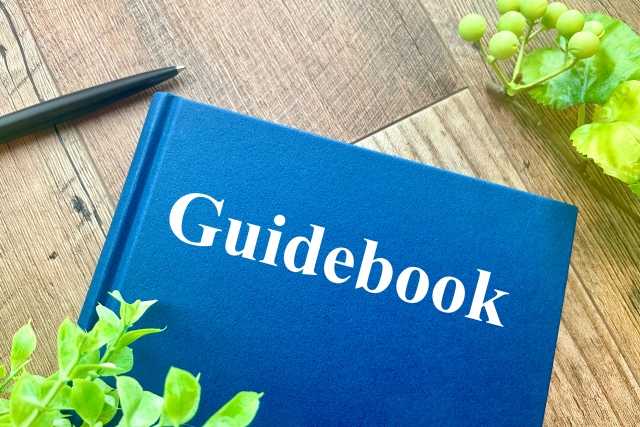
ハピタスに会員登録がまだの人は、まずは無料会員登録を済ませてしまいましょう。
ハピタス登録はメールアドレスと電話番号さえあれば1分で完了します。
電話番号がなくても会員登録をすることはできますが、そのままではハピタスで貯めたポイントを交換できなくなっています。
ハピタスに登録する手順は以下の通りです。
- ハピタス登録の紹介リンクを押す
- メールアドレスを入力:Gmailなどのフリーメールがおすすめ
- パスワードを入力:半角英数字を使用して8文字以上で入力
- ニックネームを入力:半角英数字20文字以内で入力
- 個人情報を入力:自身の正確な情報を入力
- メールアドレス認証:ハピタスに登録するために必要
- 秘密の質問設定:貯めたポイントを交換するために必要
- 電話番号認証:貯めたポイントを交換するために必要
- 登録完了
まずはパソコンかスマホで以下の登録バナーを押しましょう。
▼ハピタス登録の紹介リンクはこちら▼
 ざくざく
ざくざく
移動したハピタスサイトの会員登録ページにある『会員登録する』ボタンを押して、ハピタスの会員登録を済ませましょう。
QRコード読み取りで登録が完結することを紹介しているブログもありますが、ハピタスオリジナルの登録QRコードは存在しません。
▼ハピタス会員登録の詳しいやり方はこちら▼


ハピタス登録のメリット・デメリット|ポイ活初心者必見
ハピタスを利用するメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイントが貯まりやすい
- 1ポイント1円で分かりやすい
- ポイント保証制度が充実している
- ポイント交換手数料が無料
- サイトが見やすく使いやすい
ハピタスを利用するデメリットは以下の5つが挙げられます。
- ポイント反映が遅い
- 会員ランクの昇格・維持が面倒
- コツコツ系コンテンツが少ない
- アプリ版ハピタスが使いにくい
- ポイント還元率は低い?
デメリットの部分は他のポイントサイトにも当てはまることがあるため、ハピタスのデメリット=ポイントサイト全体のデメリットと言える部分があります。
ハピタスで効率的にポイントを貯める方法|初心者でも簡単
ハピタスにはポイントを稼げるさまざまな広告が充実しています。
それらの広告を利用して単発で1万ポイント貯めることは決して難しくはありません。
毎月1万ポイントを継続して貯めるにはハピタスのコンテンツをフル活用していく必要があります。
- ネットショッピング広告を利用する
- 無料体験系サービス広告を利用する
- リサイクル系広告を利用する
- クレジットカード発行・口座開設系広告を利用する
- 外食モニターコンテンツを利用する
- 友達紹介コンテンツを利用する
ポイ活で貯めたポイントは手数料無料で現金や電子マネーなどに交換することができます。
ハピタスのポイント失効に注意
貯めたポイントは1ポイント残らず使い切ることで意味があるものになります。


ハピタスのポイント有効期限は以下の通りです。
第10条(当サイトのサービス制限及び承認抹消)
1.会員が以下の各号に掲げる事項に該当した場合、弊社は第2項に定める措置をとることができるものとします。
H. 180日以上当サイトへのログインがない場合。
V. 最後にポイント獲得した日から180日が経過した場合。
一定期間ログインしなかったりポイントを獲得しない状態が続くと、獲得ポイントが失効してしまうので注意しましょう。
まとめ:FANG+・NASDAQ100「どっち」を選ぶべき?質問と回答
- NASDAQ100は初心者・長期投資向き
- FANG+はリスク許容度が高い人向き
- 両方を組み合わせて分散もおすすめ
FANG+とNASDAQ100は、どちらも米国の成長企業に投資できる魅力的な選択肢です。
リスクを抑えて安定した成長を目指すならNASDAQ100、短期で高リターンを狙いたいならFANG+が向いています。



自分のリスク許容度や投資目的に合わせて選び、長期・積立投資を基本にするのがおすすめです。
▼ハピタス登録はこちらからがお得▼
▼ハピタスの証券広告特集▼